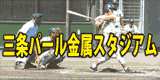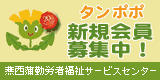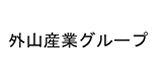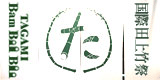|
|
盆の15日にもかかわらず水燕鎚工会作品展解説会に約30人が来場 (2010.8.16)
|
|
|
|
|
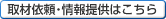
|
8月22日まで水燕鎚工会作品展が開かれている燕市産業史料館で15日、作品解説会が開かれ、伝統的工芸品に指定されている「燕鎚起銅器」の巧の技を伝承する水燕鎚工会会員による解説を約30人が来場して聞き入った。
 |
|
15日に燕市産業史料館で開かれた水燕鎚工会作品展の作品解説会
|
作品展期間中に3回、作品解説が企画され、この日はその2回目。昭和24年生まれで日展会友の高橋純一さん=燕市分水桜町1=と、同32年生まれで新潟県工芸会会員の椛澤伸治さん=三条市東三条2=が解説を担当した。
 |
 |
|
椛澤伸治さん
|
高橋純一さん
|
鎚起銅器は一枚の板を打ち延ばして立体を形作るのが基本だが、延ばすだけではなく、打つことによって縮める「しぼり」と呼ぶ技術も欠かせない。さらに彫金の片切りや線彫り、打ち出しといった技法をていねいに説明した。
漆、緑青、煮色、赤銅、金ケシなど、銅を発色させるさまざまな技法の手順や難しさをわかりやすく紹介。抽象的な作品を手掛ける高橋さんは「(モチーフは)その人が勝手に判断してくれてもいいわけです」、椛沢さんは「使っていくとだんだん色の変化を生んでいくんです」などと魅力を語った。
水燕鎚工会は、鍛金6人、彫金2人の8人が会員で、1人が三条市のほかは燕市。今回は会員が制作した花入れや茶道具、オブジェ、レリーフなど49点を展示している。最後の3回目の作品解説会は22日午後2時から開き、岡本國雄さん、広田温樹さん、深海晃一さんの3人で解説する。
関連リンク
|