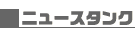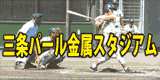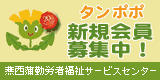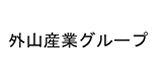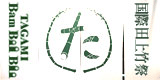桜ほころぶ弥彦で湯かけまつり 「弥彦にしてよかったね」 (2025.4.7)
「越後の春は弥彦から」とうたう「弥彦湯かけまつり」が6日、桜のほころび始めた新潟県弥彦村で行われ、一般参加者も一緒に神湯を載せた湯曳(ひ)き車をひいて盛り上げた。

一般社団法人弥彦観光協会(河村信之会長)の主催で1987年(昭和62)から毎年、桜の咲くころに行われている行事。弥彦公園の湯神社で受けた神湯をたるに詰めて湯曳き車に載せ、弥彦駅から温泉街を通って弥彦神社までひいて奉納する。
開運厄除、無病息災、商売繁盛、交通安全、学業成就などを祈るとともに、弥彦神社や弥彦温泉で県内有数の観光入り込み客のある弥彦観光のシーズンインを告げる。
午後から駅前で出発式を行って始まった。弥彦よさこい添の演舞、弥彦芸妓(げいぎ)の祝舞の披露のあと、弥彦神社氏子青年会(黒津一彦会長)の木遣(や)りで出発。講中も参加して湯曳き車の綱を引いた。

湯曳き車の前後に綱引きのような太い綱が2本ずつ伸びている。一般参加者は軍手をつけて湯曳き車の綱を握り、一度に200人ほどが綱を引いた。「えんやー!」などのかけ声に合わせて綱を上下させたり、蛇行したりしながら湯曳き車を引いた。
時々、合図とともに主に湯曳き車の後ろの後綱(あとづな)を握る弥彦神社氏子青年会の会員が進行方向とは逆の後ろに引いて綱引き状態に。湯曳き車の上からひしゃくで会員に神湯をじゃばじゃばとかけ、会員はずぶぬれで必死の形相で綱を引き、互いに負けじと必死に綱を引いて盛り上がった。

道中では、湯曳き車の上からひしゃくで神湯をまき、神湯にひたした青笹を沿道の見物客の頭の上で振る“湯かけ”を行って払い清めた。
途中の休憩でも、弥彦よさこい添弥と弥彦芸妓のほか、氏子青年会小若がたる太鼓の演奏、氏子青年会が一宮甚句などを披露。7月に弥彦で行われる重要無形民俗文化財の弥彦燈籠(とうろう)まつりを想起させる。
弥彦神社の一の鳥居に到着すると、弥彦山太鼓が迎え太鼓で湯曳き車を迎えた。参道を手水舎前まで進むと湯曳き車から3基のたるみこしに神湯を移した。1基ずつ順番に拝殿に向かい、神湯が空っぽになると激しくたるみこしをもんで奉納した。後半は雨が降り始めたが、大ぶりにはならず、最後までほぼ予定通りに進行した。

弥彦駅前から続く停車場線や弥彦公園にはたくさんの桜の木があり、桜の花が見ごろになると花見客でにぎわう。この日、新潟地方気象台は新潟の桜(ソメイヨシノ)の開花を発表。上越市の高田城址公園で桜の開花宣言があり、弥彦の桜は花がほころび始めた。
どこに出掛けようか迷って弥彦を選んで女性のグループは「弥彦にしてよかったね」と湯かけまつりを楽しんでいた。



























三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com