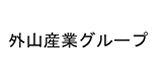三条信用金庫の職員16人が宮城県石巻市・水産加工品メーカー「木の屋石巻水産」で木製パレットの洗浄などのボランティア活動 (2011.12.25)
三条信用金庫の職員16人が18、19の2日間、東日本大震災で津波に見舞われた宮城県石巻市・水産加工品メーカー「木の屋石巻水産」で、へどろなどのついた木製パレットの洗浄などのボランティア活動を行った。

参加した16人は、西潟精一理事長をはじめ、「被災地の一日も早い復興を」と呼びかけに応じた20歳代から50歳代前半の職員。18日朝、バスに乗って出発し、昼過ぎに石巻市に到着し、信用金庫のセントラルバンク・信金中央金庫の仲介でボランティアの活動場所などを確認。車窓から市内を見て松島町の宿泊先に入った。

翌19日午前9時ころから「木の屋石巻水産」でボランティア作業を行った。同社の「鯨大和煮」の巨大な缶詰は石巻市の観光シンボルでもあったが、津波で流されて今度は石巻市の被災の規模を知る象徴的なものになった。同社工場は津波で壊滅し、泥やがれきに埋まった約80万個のサバの水煮などの缶詰をボランティアなどが拾い集め、洗浄して復興支援のために「希望の缶詰」として販売する活動を展開したことが全国でも注目を集めた。
同信用金庫職員は、同社の木製パレットを洗浄した。すのこ状のパレット全体にこびりついたへどろやサカナか重油かわからない油分などの汚れすべてをへらで削り取り、はがしてからデッキブラシを使って水で洗い流す重労働。現地でボランティア活動の指導をするボランティア2人とともに作業した。

今回のボランティアに参加した同信用金庫人事教育部の渋谷恒夫次長の話では、石巻市内へは高速道路のインターを降りてすぐは、三条・燕インター付近の須頃郷のような雰囲気で被災地のように見えなかったが、山を越えてトンネルを出た瞬間から景色は一変。別世界が広がったのを思い出す。
震災から9カ月もたつというのに、がれきや廃車が山と積まれ、街灯は倒れたまま。田んぼには船が打ち上げられたままで、火災のあった地域では焼け焦げたまま残る建物も。震災のときから時計が止まったままのような被災地のようすを体感した。

あまりの手つかずの状況に復興の時がくるのだろうかとか思うほどで、被災地以外の自治体でがれき受け入れの議論があるが、まずがれきの山をなんとかしないと復興が始まらないという印象を受けた。
ボランティアでは、へどろなど乾燥した汚れをはがすのは力が必要なうえ、食品なのでていねいさも要求される地道な作業。現地も気温が低く、思うよりも重労働で、雨具にマスクの職員は汗だくで作業した。

今も水産物などの腐敗臭が鼻をつくなか、泥水などがかかるのも気にせず、黙々と作業を続けた。作業は思うようにはかどらず、1日だけでなく継続した活動をするに越したことはないとも感じた。
被災地への往復の途中で職員は土産をどっさり買い込み、経済活動を支援する方向での被災地支援もある。石巻市には震災直後から緊急消防援助隊をはじめ新潟県からも多くの支援が行われた。今回、現地で「三条信用金庫」の三条の名前を知ると、「三条や長岡(の消防が震災後)が一番早く入ってくれた」と言われ、新潟への感謝の気持ちを表されたとも話していた。
- 三条信用金庫(新しいウィンドウで開く)
- 株式会社 木の屋石巻水産(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com