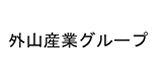燕市産業史料館の企画展「やかん展」にあわせて戦後に隆盛を極めた燕市の洋食器産業をデザインから牽引した荒沢紀一さんが代表作のケトル「K-2」を取り上げて対談 (2012.5.14)
燕市産業史料館では、11日から27日まで開いている企画展「やかん展」にあわせて13日、展示している小林工業=燕市南5=のケトルをデザインした荒沢紀一さん(69)と同史料館学芸員による対談を行い、約20人が来場して荒沢さんがデザインに込めた機能や情熱に聴き入った。

荒沢さんは三条高校、武蔵野美術学校本科西洋画科を卒業、小林工業に入社した。1970年に退社して荒沢紀一デザイン事務所=燕市白山町1=を開設。小林工業とは親せき関係で学生時代からアルバイトで同社のパッケージデザインを手掛けた。燕市で洋食器の貿易が全盛だった昭和40年ころ、輸出用デザインからの脱却、日本にふさわしいオリジナルデザインを目指した。
受賞したグッドデザイン賞は64点を数え、ロングライフデザイン特別賞は30回、内閣総理大臣賞も受け、インダストリアルデザインに大きな足跡を残す。70歳を前にした今も現役だ。

荒沢さんはまず自身の立場を説明。工芸品、美術品と違って量産のデザインであり、「品質を守ったうえで、できるだけコストダウンを図り、安く作って多くの人の手に渡すのが使命」。10人中5人、6人がいいと思ってくれるのが大事で「当然、シンプルな形になるし、くせのない飽きのこない形というものを目指すことになる」と話した。
ケトルのデザインは、やけどをしない、熱源の問題、操作性を求められるなど条件が多く難しいと言う。1979年にグッドデザイン賞を受け、その後、ロングライフデザイン賞も受けたティーケトル「K-2」を取り上げた。

水が美しく流れることにこだわり、「水の流れには自信がある」。日本に昔からある断ち切りというデザインを生かした。水の量が減ると重心が変わる、注ぎ口の高さは満水のラインより少し上にないとこぼれる危険がある、持ち手に熱が伝わりにくいように胴体から2センチほど離した、持ち手のプラスチックは金属ごと型に入れる焼き込みでシンプルで美しい造形を実現したといった、毎日のように使ってもいても気付かないようなさまざまな工夫が凝らされており、来場者は「おーっ」と思わず声を上げてうなづくこともあった。
発売当時、ふつうのケトルが2,000円、3,000円なのに対し、「K-2」は1万5,000円もした。百貨店へ持ってたら、扱える価格だと積極的に扱ってもらえ、「市場と商品がマッチした」。

この前身のモデル「K-1」は、グッドデザインの審査で値段が高いと落とされ、雑誌でも酷評されたが、百貨店に並べたら売れ、その翌年に通産省が都内の百貨店を調査してケトルの人気を調べたら「K-1」が第1位だった。「それを知って去年、Gマークで落としたケトルをことしは合格させるからぜひもういっぺん出してくれと言われたことがあって、うれしかった」。
自身の作品は「早過ぎた」とも。40年前に幼児用のスプーンを試作したが、百貨店にも誰にも相手にされず、立ち消えになっていたが、それから30年ほどたってそのサンプルを百貨店に見てもらったら、おもしろいからやろうとなり、もう1回、型を起こして発売したら結構、売れ、デザインで賞も取った。「今は反省してあんまり先へ行くことはなくなった」と笑わせた。
エピソードも満載で、外からは知ることのできないアイデアがぎっしりと詰まっており、戦後の燕の洋食器産業をデザインで牽引してきた巨人の話は、先人に学ぶこと、視点を変えること、極めることなどの大切さを教えてくれた。
- 燕市産業史料館 -新潟県燕市-(新しいウィンドウで開く)
- LUCKYWOOD|小林工業株式会社(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com