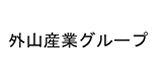縄文時代の豊かな文化や世界観を読み解く小林達雄國學院大學名誉教授が講師の「さんじょう遺跡物語講演会」約150人が出席、山井太スノーピーク社長との対談も (2012.7.8)
8月5日まで三条市諸橋轍次記念館で開かれているさんじょう遺跡展示会「五十嵐川流域の火炎土器」にあわせて、7月8日午後2時から「さんじょう遺跡物語講演会」が開かれた。約150人もが出席し、長岡市出身の考古学者で新潟県立歴史博物館名誉館長、國學院大學の小林達雄名誉教授の講演、さらに会場の地元に本社を置くスノーピークの山井太社長との対談に聴き入った。

講演会は「火焔土器のクニと五十嵐川流域の縄文人たち」、対談は「縄文人のデザイン力〜くらし・人生・モノづくり〜」がテーマ。「縄文といえば小林達雄」と言われるほど、小林名誉教授は縄文時代の研究者として知られ、一昨年3月にNHKで放送された「爆問学問」の「2010年 縄文の旅」の回に出演している。
近年、「縄文ブーム」の再来かと言われるほど縄文時代に注目が集まるなか、小林名誉教授の講演を県内で聴ける機会はめったになく、考古学や歴史に興味のある人のほか、県内の自治体関係職員、さらにスノーピークファンも含めて会場は満杯の盛況だった。
講演会で小林名誉教授は、火炎土器については講演の終盤でふれ、主に縄文時代について話した。旧石器時代から縄文時代になると定住的なムラを形成するようになった。その恩恵にあずかったのは足腰が弱くなる老人。それまでは、まだまだ孫と暮らしたいと思っても身を引くよりなかった。
縄文時代の竪穴住居は、ワンルームで周りを壁に囲まれ、真ん中に炉があった。煮炊き用ではない。エスキモーでも調理は外でする。「最も家族が顔を近付けて互いの顔の動きを確認しながら」過ごす場所になった。そういう空間が古墳時代、奈良、平安になるとなくなったが、再び火を囲む重要性がわかり、いろりになった。

今の住宅は機能分化した。便利なようでいて「大事なものがどんどん忘れられ、そぎ落とされた」、「ごちゃごちゃしているという価値にだんだん気付かなくなった。ごちゃごちゃしているなかにこそ、いろいろな可能性が生まれる」と劣化した。
「ある政党は仕分けしてそのあとどうなっちゃったかわかんないですけど」、「途中でぽしゃったのはいいことだったかもしれない」と政治談義もはさみながら、「もっとごちゃごちゃしているのが、一部屋づくりの大事なこと」と、子どものころのあこがれた、子ども自分の部屋をもつ米国的な住宅の形を否定した。
何千年も前に火を燃やし続けた跡が、今でも遺跡からわかる。狭い家の中に炉をもち、奥に立石を立てる。それがその後の神棚や仏壇につながる。そこは「家族としての絆を確認し、強めるスペース」で、「それは一部屋づくりじゃなければ果たせなかった」、「もしかしたらいちばん必要なのは神棚や仏壇だったのかもしれない」。さらに話題は膨らんで、住宅金融公庫の融資制に問題があるとして、「今の世の中、霞ヶ関が主導するとんでもない方向をわたしたちは歩まされていると身につまされますね」。

縄文時代は、今と同じように言葉を操ってしゃべっていたと考えてもいいとする。人間には最初から言葉を操れる言語中枢が発達していた。世界中で自然の中に生きるものと人間を分かつ「人」という言葉をもち、日本のイエとムラ、ウチとソト、ハラ、ヤマと区別する概念を話した。
縄文時代は1万5千年以上前に始まって1万年以上続いた。人類の歴史でひとつの枠組みで1万年以上も続いたのは奇跡的。縄文人はムラのソトに広がっている縄文人環境としてのハラは、食糧倉庫であり、資材倉庫として利用した。ちゃんとした山菜採りは全部、採り尽くさない。それは基本的な人間としての能力といえる。
「われわれは縄文時代からずっと離れ、欧米からのいろんな知識も受け入れたし、追い付け、追い越せで頑張ってきたし、わが大和民族は大したもんだと思っても、実は日本人的な考え方で私たちはまとまってる。それは縄文時代1万年がものすごく影響している」と考える。
「縄文時代は日本列島を舞台にした歴史の端書きやプロローグではない。ちゃんとした歴史がもう縄文時代から始まってるんです」、「そのときに身に付いたものがいまだに継承されて、見え隠れしながらわれわれの今の時代に続いているということをいろいろな場面で知ることができる」。小林名誉教授はそれを「文化的遺伝子」と言う。
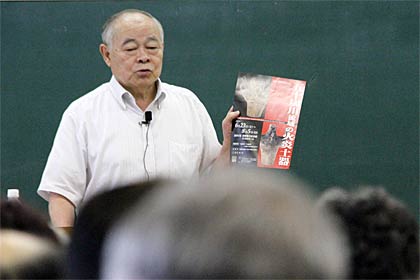
10年ぐらい前からその文化的遺伝子は言葉であるとわかってきた。そのひとつが日本語に見られる擬声語。春の小川がさらさら流れ、鳥が「てっぺんかけたか」と鳴く日本語の音素は115しかない。中国は440、英語で2万以上。「風の音も115の音の範囲でしか聞いていないからキャッチできる」、「音としてだけでなく対話している」ことで、日本語には圧倒的に擬声語が多い。それは「自然と話をするためだったのかもしれない」。
火炎土器については、終盤で「簡単なんです」とふれた。「火炎土器のクニ」は今の新潟県、それは古代の越後、さらにそれは火炎土器のクニ。「これでもう、それ以上いらない。あとは皆さん、火炎土器を見てください」。
火炎土器は「岡本太郎もひっくり返るくらいすごかった」。口に大きな突起があり、こうした形状は世界中どこにもない。弥生土器になると突起が無くなる。「便利がどうか、使い勝手がどうかを超えて、ここに込められたのかも。それは哲学です。世界観です。宇宙観です」。
その火炎土器が雪国で生まれたのは、雪国だからこそ。信濃川流域にしか存在しないのは、半年も雪で閉じ込められるから。「ずーっと抑えられていたのが爆発する」と必然性を示した。

続く対談相手の山井社長が代表に就くスノーピークはアウトドア用品を手掛ける。同社は藤ノ木遺跡から出土した鉄鍋で実現された今の技術でも難しい薄い鉄や現代でも通用するデザインにインスピレーションを受け、「燕三条極薄鋳鉄」と名付けたダッチオープンを開発していることなどから、今回の対談の依頼があった。
山井社長の考えるアウトドアは「現代人が文明の中で失ったものを取り戻すプロセス」。自然の中で人間性の回復、家族の絆を取り戻す、原始的な生活を体験して現代の生活をレビューすること。縄文時代の生活は「僕の目指しているものと非常にだぶっている」。

小林名誉教授は前日、スノーピーク本社を訪問して琴線にふれるものがあったと言い、山井社長が目指すのは「やっぱり縄文土器なんです。弥生土器じゃなくてね」、「ちゃんとした形を求めてる」、「非常にはっきりした哲学をお持ち」と分析した。
山井社長は「ほかの会社が作っているようなものは決して真似をしない。世界で最初にスノーピークが出すものが多い」、「ふるさとや母国に対してすごく誇りをもっていて、できたらそこから生まれてくるもので世界と勝負したい」というポリシーを話した。
「スノーピークのいちばんの武器は日本人であるということの結果、自然に対する情緒感が非常に発達している。それは欧米のわれわれのライバル会社と比べると、彼らには見えないものがわれわれには見える」。それが繊細な作り込みや自然のなかでのデザインの大胆さにもつながる。
そんなスノーピークに対して小林名誉教授は、「取り組みの仕方が、姿勢が弥生じゃないんですね。縄文的だと思うんですよ」と“らしい”分析。単なる機能としての役割を考えながら、独自の新しい形を模索し、真似をしない。それでいてすごく真似して、徹底的な真似人でもあると山井社長を評した。

その流れで小林名誉教授は、自身のモノやデザインに対する考え方も。縄文土器と付き合っていても、今の人がやろうとしていることの意味がわかる。「できあがった形には物語があって、由緒、来歴がある。由緒、来歴があるものは廃れないし」、一度、不人気になっても「復活する」。これはという製品を作れば、ちゃんと業績が上がる。それは信念であり、「単に形ではなく、自分の思いを込めている。縄文土器は彼らが思いを込めて作った」。
2人で、縄文人が、夏至や冬至、春分や秋分の日の出、日の入りの位置に注目して建物などを作ったのに、現代は忘れ去られていることについても話した。
小林名誉教授は、欧米で「縄文」という言葉が通用し、「土偶」という言葉も定着しつつあり、その哲学、由緒、来歴を形に表すことが大切で、「縄文の森」を作って苗木を実費販売したり、火炎土器をモデルにしたキャンピンググッズを超えたデザインのモニュメントの設置を山井社長に提案した。
対談のアーカイブ(画像は静止画)
- さんじょう遺跡物語展示会『五十嵐川流域の火炎土器』展示説明 - 三条市(新しいウィンドウで開く)
- スノーピーク オフィシャルサイト アウトドア/ナチュラルライフスタイル用品 製品 製造・販売メーカー(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com