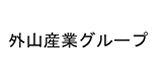燕三条デザイン研究会×北川フラム講演会、約50人が出席して北川さんから越後妻有の大地の芸術祭などについて聴く (2013.6.28)
燕三条デザイン研究会(玉川基行会長)は25日、燕三条地場産業振興センターリサーチコアで燕三条デザイン研究会×北川フラム講演会「繋がる世界の地域〜越後妻有・水土・瀬戸内の経験から〜」を開き、約50人が参加した。

北川さんは1946年、新潟県高田市(今の上越市)生まれで、東京芸大美術学部を卒業。ことしも7月20日から十日町市と津南町を合わせた妻有地方で現代アートを山間地に解放した3年に1度の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」が開かれるが、スタートした2000年からその総合ディレクターを務める。
07年から新潟市美術館館長を務め、09年に水と土の芸術祭ディレクターを兼務。10年から瀬戸内国際芸術祭総合ディレクターとして「海の復権」を掲げ、現在、同芸術祭2013が開かれている。
講演で北川さんは、前提として燕三条地域のことはまったく知らず、「十日町でやってきていることが何らかの形で参考になれば」と前置き。自身の“美術”の定義は、「皆さんが考えている美術とはまったく違う」、「食べ物、料理、庭、掛け軸、床の間、祭り、食べ物で使う茶わんも広く美術と思っている」とし、「まったくいい加減、だらしない、あるいは何でもあり、めちゃめちゃっていうものも入って美術」で、「(母校の)東京芸大の芸術、美術にはまったく興味がないし、いやだという立場でやってる」ときっぱり。
いったん、前夜に初めて見たという、できたばかりの妻有のプロモーションビデオを上映、鑑賞してもらってから再び話した。「観光」ではなく、幸せを感じるという「感幸」がある。妻有では「人がたくさん来られていることの観光が、じいちゃん、ばあちゃんの感幸になるということで、ここにおいて行政上と大地の芸術祭の一応、社会的、政治的なつじつまが合う」。
今までの地域づくりは効率化、情報化、一極集中だった。大地の芸術祭は作品を地域に点在させた。最初は客が少なく、関係6市町村長から作品を1カ所に集めるよう言われた。これが汐留、丸の内、六本木ヒルズ、ミッドタウンで行われたこと。最新の情報に最短でアクセスできるという一極集中がすべての原理になっている。しかし、妻有でやろうとしたのは、「一極に集中するんじゃなくて、約200と言われている妻有の集落、全体に拡散しようということ」。

自分の住んでいる集落のことしにしかリアリティーがない。「これが約5、60年前まで、車社会になるまで半年、雪の中で助け合って生きてきた人たちのリアリティー」で、「人間のリアリティーに寄りそうしかない」、「それしか確かなものがない」。2000年は、県や国が進める合併のための政策として大地の芸術祭は行われたが、「わたしたちはそれに百八十度、違う動きに入った」。
続けるうちに来場者の反応に変化が見られた。足に返ってくる土の弾力、むんむんとする草いきれ、濃密な集落、ほおを渡る風。「このさわやかさは何なんだろうということ。これがいろいろな形に変わってきた」。
過疎高齢化による地域力の衰退、効率化による地域切り捨て、場当たり的政策によるエネルギーの消耗が起きた。大地の芸術祭では「人間は自然に内包される」を基本理念に、地域資源の発掘、他者とのかかわり、世代、地域、ジャンルを超えた協働などの目標を掲げた。
そして大地の芸術祭でできたことは、お年寄りが元気になり、集落が参加し、行政が変わった。場を生かす世界の美術の可能性を変えた。まったく思わないことが起きた。それは都市の人間たちが圧倒的に地域を求めている。「これはもう信じられない」。都市からの流動化、移動が起きた。
できなかったこと。3年間で地域が出しているのは1億円。それがメンテナンスでなくなっている。自立的な展望はまったくできていない。そのため昨年から全面的な見直しに入った。地元サポーターもいない。スタッフやサポーターの学びの場になっていない。
3年ごとに地域の高齢化はすさまじいペースで進んでいる。作品の中身が弱くなってる。地域の大課題、政策とのすり合わせに入っていかなければならない。とはいっても、中心市街地の活性化は決定的に重要で、そうしたことを考えていかなければならない。
北川さんは、その後も具体例を示しながら大地の芸術祭について話した。燕三条デザイン研究会会員以外では、観光や地域づくりに関連した部署の公務員やまちづくりに興味のある人、さらに北川さんのファンという人も。北川さんは大地の芸術祭を世界最大規模の国際芸術祭につくりあげた立役者だけに、そこに込めた思いや考え方、手法を学ぼうと熱心に聴講していた。
- 大地の芸術祭の里(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com