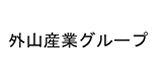養豚場で撮った写真集『人』を出版した燕市出身の写真家、渡辺一城さんが8月、燕市産業史料館で凱旋初個展「豚」 (2014.7.22)
養豚場に取材した写真集『人(ひと)』を出版した燕市出身の写真家、渡辺一城さん(35)=東京都新宿区=。その凱旋(がいせん)初個展「豚」が8月1日から31日まで故郷の燕市産業史料館で開かれ、写真集に収録した豚を撮影した作品を中心に新作数点を加えた30点近くが展示される。

渡辺さんは98年、東京工芸大学芸術学部写真学科に入学した。キャンパスは神奈川県厚木市。大学へ行くと風向きによって時々、臭くて懐かしいにおいが鼻をついた。近くに養豚場があるとすぐにわかった。「西の方角に養豚場があるのは、ふるさととまったく同じシチュエーションだった」(渡辺さん)。ふるさとのイメージがわき上がった。
燕市小中川に生まれた。実家の近くに“豚団地”と呼んだ場所があった。今は2軒しか残ってないが、当時は5、6軒の畜産農家が養豚場を建てていた。しかも母の実家は近所の笠原精肉店。98年に店を閉めるまで祖父母が営んでいた。保育園の散歩で、何度も豚団地まで歩いた。豚はふるさとの原風景としてすり込まれた。

引き寄せられるように大学そばの養豚場へ。有限会社臼井農産だった。頼んで写真を撮らせてもらうようになった。それからもう15年以上も撮り続けている。ふだんの仕事ではデジタルカメラしか使わないが、豚はフィルムにこだわる。
最初は“デュロック”と呼ばれる種豚の迫力に圧倒された。撮り続けるうちにファインダー越しに見る養豚場が違った風景に見えてきた。それがふるさとの家族であることに驚いた。「最初は、なぜ豚を撮るかまで掘り下げなかった。行き着いたのは、デュロックにおじいちゃんの横顔が重なった」。その再現をと、慌てて新潟へ帰って祖父の写真も撮った。「撮ってるうちに目や仕草から豚が人に見えてきた。豚の中に家族も見えてきた」。

「どうして今、この場所に自分が立っているのかと意識すると、親に感謝しなければとわかった」。豚が生まれ、成長し、殺され、肉の塊の食品となる過程を切り取った。日常的に豚を意識しながら育った渡辺さんが、命や生の連鎖を考えさせられたのは当然だった。
「これまでの人生を振り返ってなぜ豚を撮っているのかわからなかった。豚も何もわからないまま死んで肉になる」。何もかもわかったわけではなく、今も豚を撮りながらふるさとや家族を投影し、自分を見詰め直している。
豚を撮るのはライフワークと言う。昨年6月15日に撮りためた養豚場の写真61カットを収録した写真集『人』を自費出版した。豚を撮りながら写真集のタイトルが“人”になったのには、こうした理由があった。


アフリカの豚や肉の写真も撮りたいし、実家が農業も営むことから2年前からコメにかかわる作品も撮り始めている。個展は写真集発刊を記念して昨年6月に新宿のB GALLERYで開いて以来2回目、故郷では初めて。
渡辺さんは「自分のなかで、ある種の区切りになると思う。自分の作品をどう見てくれるのか、もしかしたら東京のお客さんと反応はあまり違わないのかもと想像したり」と心待ちにしている。現在、渡辺さんは3人の写真家と4人で2010年に設立した共同写真事務所「4×5 SHI NO GO」に所属している。

史料館は月曜が休館日で、開館時間は午前9時から午後4時半まで、入館料は高校生以上300円、小中学生100円。A4判88ページの写真集も税込み4,320円で販売する。
8月3日は午後2時からトークショー「MINI講演会」を開き、B GALLERYキュレーターの藤木洋介さんと史料館の斉藤優介学芸員をゲストに渡辺さんが講演、トークを行う。さらに8月17日は「渡辺一城 写真館」を開き、正午から午後1時までを除く午前10時から午後3時まで、渡辺さんが4×5判の大きなポラロイドカメラで1カット3,000円で撮影してくれる。
- 燕市産業史料館 -新潟県燕市-(新しいウィンドウで開く)
- 4×5 | SHI NO GO(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com