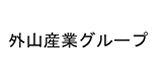工芸界のトップランナー、玉川堂、中川政七商店、能作の3社がトークショー (2016.4.25)
16日から5月22日まで燕市産業史料館で開かれている鎚起銅器の玉川堂(燕市中央通2・玉川基行代表取締役)の創業200年を記念した「玉川堂創業二百周年展」の関連イベントとして24日、同史料館で「アニバーサリーイヤー伝統三社トークショー」が行われた。

玉川堂七代の玉川基行さん、手績み手織りの麻織物を扱う中川政七商店(奈良市東九条町)十三代の中川淳さん、鋳物メーカーの能作(富山県高岡市戸出栄町)社長の能作克治さんの3人によるトークーショー。創業200年の玉川堂をはじめ中川政七商店はことしで創業300年、能作は創業100年になる。
この3社が同時にアニバーサリーイヤーを迎える奇跡的な符合にちなみ、ことしに入って中川政七商店が企画、能作が徳利(とくり)、玉川堂が猪口(ちょこ)を製造した「六角形 徳利・猪口」(54,000円)を中川政七商店の三百周年記念商品のひとつとして発売しいる。

今度は3社の代表がトークでコラボレーションをと企画したもので、各社が沿革などを話してからトークに移った。玉川さんは200年の歴史で5度のピンチがあったことを話し、バブル崩壊後の危機では半分の社員を解雇し、会社に入ったときの自身の役員報酬は5万円だったと言えば、能作さんは2003年に高給だった新聞記者を辞めて会社に入ったときは手取りで月9万円だったと明かした。
能作さんは養子の方が業績がいいというデータを紹介。中川さんは次の十四代は中川の血脈ではない人にやらせたいと考えているが、それには借金のない状態しなければならないという覚悟がある。3社とも女性の採用が増えており、中川さんは女性の優秀さを強調した。

中川さんは、工芸と作家は似て非なるものと指摘した。作家を売れると値段が上がる。伝統工芸と呼ばれるものは使われなくなったものが大半で、車はすでに100年以上の歴史があるが、進化を続けているので伝統工芸とは言われない。
玉川さんは「伝統と伝承は違う」と言い、革新を続けるのが伝統で、それが「これからの玉川堂」。能作さんは伝統という言葉は好きではなく、伝統的工芸品は「保護しなければいけないという姿勢」。中川さんは工芸は石器の時代から自分の必要なものを自分で作っていたが、作って売ることがもうかるようになって作り手と使い手が離れ、「もうちょっと距離を縮めないと」。玉川さんは「江戸時代のような“用と美”に戻ると思う」との考えを示した。

能作さんは、伝産でも大量受注に応えられる能力をもつ必要があるとし、「伝産、工芸だから待ってくれは違う」。中川さんはどこの会社も予算表がなく、経営がなく、それを助長するのが補助金と言い、能作さんも補助金をあまりにも穴埋めに使うことが多いと指摘。玉川さんも海外の展示会の補助金を受けて出展しても、出展だけで終わり、本来の目的であるその後の海外での仕事につなげようという意欲がないところが多いと話し、3人から補助金の在り方の見直し、補助金を利用する会社の意識をあらためるよう求める声が相次いだ。
海外展開については、中川さんはまったく取り組んでいない。能作さんはミラノに直営店をもつが、ニューヨークにも展開したいと考える。玉川さんも海外へも直営店を展開したいと考えているが、同社のことだけでなく、「燕三条地域に外国人から来てほしい」と地域のブランド化やインバウンドのねらいもある。中川さんも「来て見てもらうのが、いちばん価値が伝わる」と賛同した。

3人ともそれぞれが実体験をありのままに話した。工芸の分野でトップランナーともいえる3人だが、ここまでの道のりは決して平坦ではなく、仕事に対する思いや覚悟は説得力があり、1時間余りのトークショーはあっと言う間だった。
来場者は定員50人だったが、予想を上回る来場があり、70人に拡大。市外から県外、首都圏から訪れた人、オープンファクトリーのビジネス化を目指す大学院生など幅広い人たちが来場し、熱心に聞き入っていた。
- 玉川堂創業二百周年展 | 燕市産業史料館 -新潟県燕市-(新しいウィンドウで開く)
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com