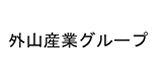「燕三条 工場の祭典」を担当した三条市職員がミステリー小説を出版 (2016.9.29)
10月6日から9日まで開かれる「燕三条 工場の祭典」はことしで4年目になる。その立ち上げから担当してきた三条市職員が、これまでの工場の祭典などを通して得た知見を生かして書いたミステリー小説を自費出版した。

書名は「庖丁の裏側」。市民のさまざまな相談に対応するN市役所の「なんでも相談課」。そこに鍛冶職人の祖父をもつ女子大生から、突然、送られてきたさびた包丁の謎を解いてほしいという相談が持ち込まれた。そのさびた包丁は女子大生が祖父と仲たがいする原因となった包丁に良く似ていたため、女子大生は祖父の元を訪れたが、祖父は行方不明になっていた。
祖父の行方を追っていろいろな包丁工場を回って謎を解くうちに鍛冶の世界を知り、ものづくりの裏側を知ることで職人の世界観や製品の見え方が変わっていった。文庫本サイズで290ページに及ぶ長編ミステリーだ。
作者は三条市経済部商工課主任、渋谷一真さん(32)。新潟大学法学部法学科を卒業して三条市役所に入庁。地域振興課、3年間の経産省出向のあと商工課に異動して6年目になる。工場の祭典は第1回から昨年まで3回は主担当を務め、ことしは副担当となった。
工場を公開する事業は全国でもあまり例がなく、前任者の残した構想を渋谷さんが形にした。初年度は手探りで準備を進め、一から十まで渋谷さんが進ちょくに目を開かせた。おかげで、見るたびにやせていくと心配されたほど、渋谷さんは心身ともに追い込まれながらもやりきった。それだけに工場の祭典に対する思い入れは強い。
ほかの部署へ異動の可能性も高まるなか、昨年の工場の祭典が終わり、それまでの経験をまとめてみたいと思うようになった。それが大好きなミステリー小説という形だった。今までまとまった物書きの経験はなく、これが処女作。いちばん好きな作家は米澤穂信氏。どうせ書くなら小説の公募賞に応募しようと、講談社主催の公募文学新人賞「メフィスト賞」への応募を前提に執筆を始めた。
昨年11月から創作にとりかかった。構想1カ月でおおまかなストーリーから人物キャラクター設定、起承転結を設計し、昨年12月から2カ月ほどで書き上げた。さらに推敲を繰り返してことし3月に完成。メフィスト賞に応募したが、残念ながら受賞はならなかった。

書籍化の話がもちあがったのも、工場の祭典がきっかけだった。9月16日から19日まで東京で開かれた「東京アートブックフェア2016」に工場の祭典がPR出展することになり、工場の祭典を撮影してきたカメラマン、神宮巨樹氏の写真集を製作、紹介することになった。
あわせて関係者から、渋谷さんの作品も書籍化して展示してはとの声が上がった。出版にかかかる費用は関係者が負担してくれ、正確には“他費出版”か。100冊を作成した。表紙カバーは工場の祭典のデザインワークを担当するSPREADが手掛け、グラデーションの箔押しという凝った手法でメタリックな質感を表現。工場の祭典を象徴するピンクの斜めストライプもデザインした。
1冊700円で、すでに60冊ほどを販売、配布した。すぐになくなると思われるが、1冊当たりの製作費は販売価格を大きく上回ることもあり、増刷の予定はない。
読了した渡辺一美商工課長は、「おもしろかった。鍛冶のことがたっぷり書いてあり、仕事で得たノウハウがいかんなく発揮されている。とくに地元の人が読むとイメージが広がるのでは。ラブロマンスとも読めた」と太鼓判を押す。
渋谷さんは「皆さんの協力が形になってありがたい。本を読んでもらい、読み切ったと連絡をいただくと素直にうれいしい」と目を細める。奥深い鍛冶の世界の魅了されたからこそ作品を完成させることができ、「鍛冶をまったく知らない人から、鍛冶に興味をもったり好きになったりしてもらえたら最高」と願う。
この夏、結婚してプライベートも充実。「次回作は同じ工場ネタで書いてみたいとは思うがまだ全然、予定はない」と照れくさそうに笑った。
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com