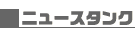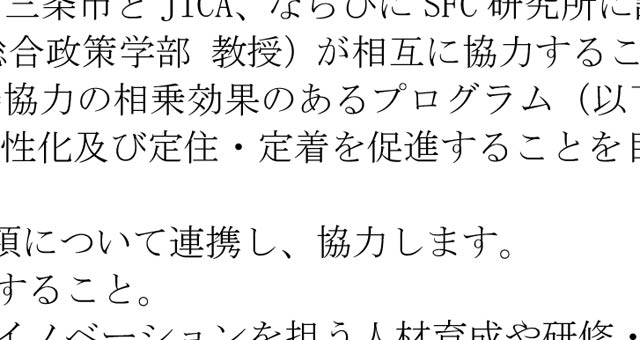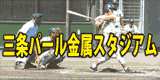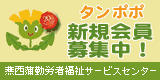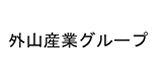三条市・JICA・慶大の3者の連携協定が外国人の移住促進を目的にしているという誤解が拡散 (2025.8.27)
21日にJICA(国際協力機構)に「JICAアフリカ・ホームタウン」に認定された国内4市に批判や問い合わせが殺到する騒動で4市のうちのひとつ、ガーナのホームタウンに認定された三条市が昨年、JICA、慶應義塾大学SFCと3者で結んだ連携協定の協力事項に移民を促進している部分があると誤解した情報が26日夜からSNSで広がっている。
この協定は「JICA地域おこし研究員プログラム」という取り組みの一環で昨年7月に締結した地域おこしと国際協力の相乗効果のあるプログラム「地域おこしと国際協力の研究開発と推進に関する連携協定」。
協定に関する報道関係者向けの文書のなかに「三条市の地域活性化及び定住・定着を促進することを目的とします」とある。この部分を外国人の定住・定着を促進するものと読み解き、移住促進が誤情報に基づくものだとする三条市の発表はうそだと主張する投稿がSNSで拡散した。
「定住・定着を促進」は外国人ではなく地域おこし協力隊のこと
しかし、三条市とJICAの間でホームタウン認定の話が始まったのは、ほんの数カ月前のこと。連携協定を締結した当時、ホームタウン認定は影も形もなく、前提になっていない。
ここでいう「定住・定着を促進」は地域おこし協力隊のこと。三条市は地域おこし協力隊の採用に積極的だが、最長3年の任期が終わると三条市を離れる人が多い。定着率の低さが課題になっていることから、協定の目的に「定住・定着を促進」加えた。外国人の定住・定着を想定した文言ではない。
先入観をもたずに読めば、地域おこし協力隊の定着のこととわかるが、今回の騒動で外国人に置き換えて理解されたようだ。
グーグルマップで三条市役所を「ガーナ市役所」と書き換えるいたずらも

地図情報サービス「グーグルマップ」では、ホームタウン認定4市の市庁舎の名称をアフリカの国名に書き換えるいたずらが相次ぎ、三条市も一時「ガーナ市役所」と書き換えられている。三条市では冷静な対応を呼びかけている。
三条・燕、県央の情報「ケンオー・ドットコム」kenoh.com